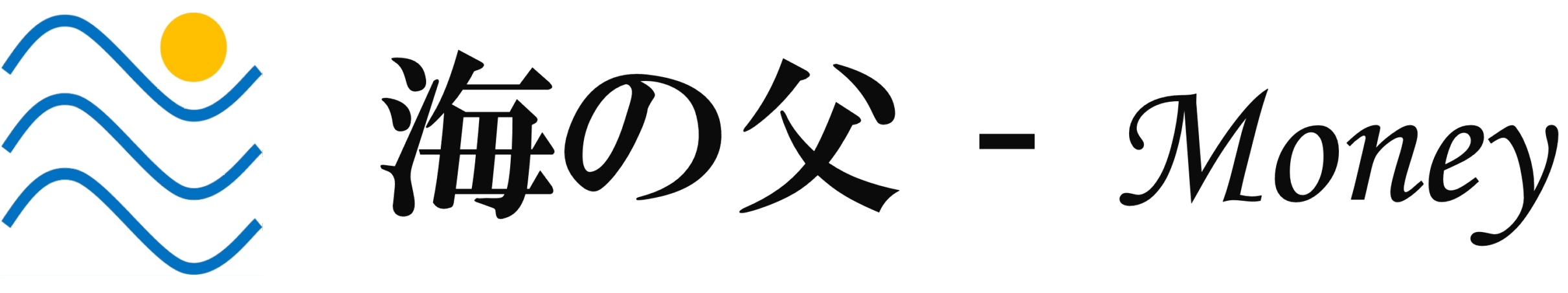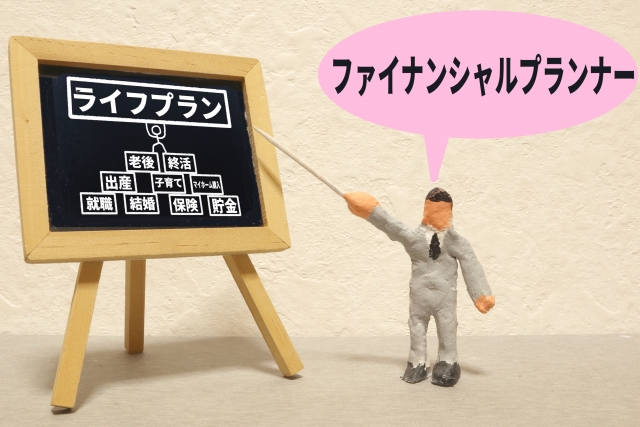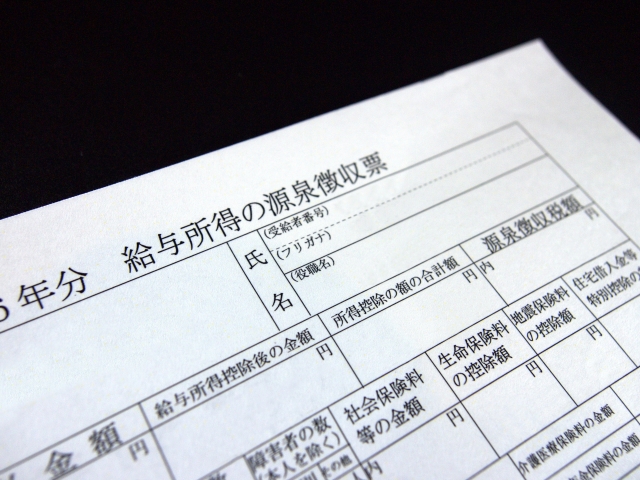今日はファイナンシャルプランナーとは何かを説明したいと思います。お金の相談はいろいろなところで行われていますが、金融機関や士業の方への相談と何が違うのでしょうか。
- ファイナンシャルプランナー(FP)は個人のライフプラン全体をもとに意思決定の支援を行う
- 業者や専門家に行く前段階でのアドバイスが中心
ファイナンシャルプランナーとは
「人生お金がすべてではない」とは言うものの、日々を生きていくためにお金が必要なことのも事実です。心豊かな生活を送るために、いろいろな希望を持ち目標を立てると思います。結婚して家族を持ちたいとか、住宅を購入したいとか、世界各地を旅行したいとか、希望は千差万別、人それぞれです。また、はっきりした希望はないけれど、なんとなくこうなったらいいな、くらいに考えている人も多くいらっしゃるでしょう。
一方で、未来は不確実であり、確実に未来を予想することはできません。そこで、希望を現実に変えていく確率をどうやったら高められるのか考えていく必要があります。希望は人それぞれですし、収入を得るのも使うのもすべて本人の意思ですから全て自己責任です。希望を目標に変え、さらにその目標を金額に換算し、支出する時期までに目標金額を蓄えていく、ということを自分でやらなければなりません。
そのためには、多くの知識とそれを前提とした意思決定が必要になります。住宅購入という大きなライフイベントを考える場合、その支出が教育費や老後資金を圧迫しないかなどの検討が必要でしょう。一つのライフイベントだけを考えるのではなく、希望する目標を達成するまでに予定されるライフイベント全体を考慮すること、これがライフプランニングです。そして、このライフプランニングのお手伝いをすることがファイナンシャルプランナー(FP)である、と言えます。FPには生活全般にかかるお金や税金、資産形成、保険、不動産、相続など幅広い知識が必要になることは言うまでもありません。
FPと金融機関や士業との違い
「お金の相談をしよう」と思った時、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しようと思われる方はまだまだ少ないのだろうと思います。住宅購入であれば不動産会社やハウスメーカー、保険であれば保険業者、資産形成であれば銀行や証券会社を思い浮かべるでしょう。また、税金であれば税理士、相続であれば司法書士や行政書士などに依頼することを考える方もいるでしょう。
不動産会社やハウスメーカー、保険業者などは最終的に商品やサービスを販売することが目的です。業者専属のFPでも、ライフプランニングまで踏み込んで相談に乗ってくれるかもしれません。しかし、業者専属ということではやはり公正中立な立場とは言いづらい面があります。また、士業の皆様はその専門性の高さで業務をされていますので、ライフプランニング全般の相談業務を行っている方は少ないと思います(一部FP資格とのダブルライセンスの方は対応されていると思います)。
前章で述べたとおり、ライフイベント全般におけるお金の知識を要求されるFPですが、FPの国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士には、他の士業には存在する独占業務がありません。独占業務とはその資格を有する者だけが行うことができる業務のことです。FPに独占業務がないということは、FPの資格がなくともFPを名乗って活動することができるということです。幅広い知識と顧客に寄り添う姿勢を持つ公正中立な良質のFPが増えていくことが望まれますが、独占業務がないことが独立系FPとして事業を成功させることを難しくしているとも考えられます。
そのような背景もあり、J-FLEC(金融経済教育推進機構)は良質なアドバイザーを認定する制度を昨年から開始し、その認定条件のひとつとして金融機関に所属していないことをあげています。良質な独立系アドバイザーが増えていくきっかけになれば良いと思います。
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。
- J-FLECでは、J-FLECが定める認定要件に合致し所定の審査を通過した個人を、「J-FLEC認定アドバイザー」(一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザー)として認定・公表しています。
※「J-FLEC認定アドバイザーになるには」より引用
ライフプランニング
ライフプランニングとはどのように行うのでしょうか。日本FP協会は、ライフプランニングについて以下のように記述しています。
ライフプランとは、自分自身や家族の将来にわたる生活設計のことである。ライフプランの前提には個人の生き方や価値観を表すライフデザインがあり、ライフプランを実現するための経済的な準備を数値化したものをファイナンシャル・プランと呼んでいる。
日本FP協会CFP®︎資格標準テキスト
「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」(2023-2024年版)より引用
ファイナンシャル・プランは価値観を反映したライフデザインを前提とするものであって、ライフプランを具体化、可視化していく作業がライフプランニングだということができるでしょう。
個人の生き方や価値観を表す
自分自身や家族の将来にわたる生活設計
ライフプランを実現するための経済的な準備を数値化
ライフプランを可視化し、ファイナンシャル・プランニングにつなげるために、通常次の三つを準備します。
- ライフイベント表
- キャッシュフロー(CF)表
- バランスシート(B/S)
ライフイベント表は自分や家族に将来発生する予定や希望を時系列にまとめた表です。どの時期にどんなイベントがあり、その費用はどれくらいになるかを具体的に考えるために作成します。
キャッシュフロー表はライフイベント表を基にした将来のイベントを行った場合の収支状況や資産の増減などを表形式でまとめたものです。
バランスシート(B/S)はある時点における資産と負債の状況を示す表です。CF表に表れない不動産やローンなどの状況把握に利用します。
これらの作成自体は難しいものではありません。日本FP協会のホームページからもこれらのツールがダウンロード可能になっています。もし興味がある方はご自身でこれらの表を埋めてみていただければと思います。
FPはこれらのツールで将来を分析し、具体的なファイナンシャル・プランニングのフェーズに入っていきます。FPは専門の業者や士業などの専門家に行く前の段階での支援を行うとも言えると思います。
まとめ
ここまで、FPがどのような支援を行うのかを解説し、ファイナンシャル・プランニングにはその前提となるライフプランニングが重要であることをお伝えしました。みなさまの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
1級ファイナンシャルプランニング技能士
CFP®️認定者
1級DCプランナー